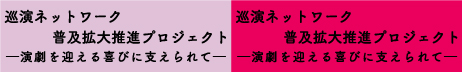2023年12月21日
『日本の劇』戯曲賞2023 最終選考委員選評 再掲載について
『日本の劇』戯曲賞2023 に関し、当法人が応募者に送付し、12 月5日にホームページに掲載した最終選考委員の選評につきまして、「差別発言が含まれるのではないか」とご指摘をいただきました。
ご指摘を受け、常務理事会で選評を読み直しましたところ、一部誤解をうむ表現があったのではないかという結論に至りました。選考委員各氏に経緯を説明し協議したところ、板垣恭一氏、小林七緒氏、内藤裕敬氏よりあらためて文章をいただきましたので、ここに掲載いたします。
日本劇団協議会では、差別を許容しないとの立場から、これからも勉強会などを通じて多様性や表現の自由についてより深く学んでまいります。最後になりましたが、貴重なご意見をお寄せ下さった方々に心より感謝申し上げます。
『日本の劇』戯曲賞2023最終選考委員選評
「日本の劇」戯曲賞2023(主催 日本劇団協議会)の最終選考会が2023年10月19日、日本劇団協議会会議室にて行われ、次のとおりに決定しました。
最終選考委員の演出家は、板垣恭一、小林七緒、内藤裕敬、宮田慶子の4氏(敬称略、五十音順)です。
※最終選考委員は5名を予定しておりましたが、眞鍋卓嗣氏はご体調不良により今回の審査を辞退されたため、残る4名で最終選考を行いました。
【佳作】 新井孔央 『杳たる月』
今年度の応募総数は63 作品。一次選考を経て最終候補作品として選出されたのは、次の5作品でした。
【最終候補作品】(受付番号順)
高山遥 『或る町』
新井孔央 『杳たる月』
七坂稲 『六畳間と女神様』
サカイリユリカ 『She lover』
中野そてっつ 『クマといくら』

■【最終選考委員選評】■
 板垣恭一
板垣恭一下読みをしている段階で「何か変わったぞ?」と感じていました。具体的には設定に工夫を凝らす物語が増えたこと、同時に物語に力強さ(=明確な方向性)がなくなったことでした。近年この場で「現状肯定型」の物語が増えていると伝えて来ましたが、今年はついに肯定さえしない「現状スルー型」の物語がたくさん登場したと感じました。
『杳たる月』はよく書けていました。キャラの書き分け、複雑な人間関係、隠された秘密、どれもお見事でした。ではなぜ佳作なのか。簡単に言うとあまり気持ちの良い物語ではなかったからです。だからこそ面白いとも感じたのでリーディング公演での演出を引き受けることにしました。『クマといくら』はクマが何をあらわしているかいまひとつ掴めませんでした。共同体を脅かす存在を秘密裏に処分しているのは佳作と同じ構造で、もう少し設定に緻密さがあればと思いました。『She lover』は簡単に言ってしまうと「不倫を通して自分の本心に気づく」という、あまり特徴のない物語でした。登場人物の心情は理解できましたが、成長物語として納得が行くほどの共感や発見が得られない点が残念でした。『或る町』は別役実さん風を極めたことが強みであり、本家と比べられてしまうという弱点にもなりました。その作者ならではを期待するこちらとしては、今後どう変化していくのかが楽しみです。『六畳間と女神様』は「信じられるものは何もない」という話が多かった中、宗教を信じる人たちという逆説的な設定が目立つものの人間描写が弱い印象です。自分の体にイレズミを施す主人公に不思議な迫力を感じましたが、それが観客に届く「何か」に昇華したらいいのにと思いました。全作の共通点は、葛藤はあるけれどそれに対して熱くなるわけでもなく、共通の罪悪感を抱えてはいるけれど、誰もが責任は取ろうとしない物語であるということでした。しかし、これは現代の我々そのものだと思うのです。
映像の世界ではAI が発達して、本物と区別がつかないヒトもどきがすでに活躍を初めています。だとすると今後、演劇の存在意義が強く見直されていくはずで。「ハッピーエンド」という近代から受け継がれた技法では、もう世界は切り取れないのだと作者たちが教えてくれた気がします。これから演劇はどこに向かうべきなのか。そもそも演劇とは何なのか。自分も考えて行きたいし、作者のあなたにも考えてもらいたいと思いました。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

小林七緒
全体として「これが書きたい!」というよりも、「こんなスタイルのものを書いてみようかな」という、ふわっとした動機の戯曲が多いように感じました。そのため、序盤はわりとしっかり構成しているのですが、物語が進むにつれてほころびはじめ、終盤が尻切れになっています。これから物語が発展する予感のところで終わってしまう。作家の中にも結論がないのかな、と思いました。
書いたものを音読してみただろうか、というのも気になりました。戯曲は、俳優の身体を通して立体化するものなので、文字の情報と声を耳で聴くのとは印象が違います。読んでみると、人物の感情がつながらない部分もはっきり見えます。この作業を通して書き上げた戯曲を見直すのは、とても有意義です。
『或る町』
別役実さんの戯曲が大好きで、別役実さん風に書いてみたいという思いが形になった作品。ベンチ、バス停、持ち主のわからないラジオやトランクなど、どこまでこの世界観でいくのかワクワクした。ただ、序盤の精密さに比べて後半ラフになり、別役さん風に書いていることの意味が薄れてしまった印象。誰のかわからないラジオを早々に消してしまったり、せっかく「男1」「女1」という役名なのに「エノモトさん」という固有名詞が出てきたり、もったいないところがある。きっちり別役さん的にやりきるか、意図的に崩すならもっと大胆にやるか。どちらかに振り切ると、面白くなりそう。「いつからかみんなバラバラになって閉じこもって~」などドキッとさせる台詞もあったので。
『杳たる月』
かなり無理な設定にもかかわらず、会話がうまいからか、グイグイ読めた。ただ、女たちの感情の動きは伝わるのに、男たちはよくわからない。設定が少し粗く、なぜここにいるのかわからない人物になってしまっているからか。殺人を犯して死体が家の中にあるのに、自分の恋愛感情にしか目が向いていない人物たちが不気味で、何も解決されず誰一人として救われない。赤ん坊に対してもあまりにも無関心でぞっとする。作者は何を描きたかったんだろう、狂人たちの身勝手なふるまいだけではないと思うのだが、伝わってこなかった。
『六畳間と女神様』
ある宗教の信者一家。かなり特殊な家なのに、そのことに無自覚な不気味さはよい。導入はいいのだが、そのまま家族 4 人に変化が起きないまま終わってしまった。娘が行方不明になったこと、なぜこの宗教にはまったのか、など変化が起きるきっかけはいくつかあったのに、揺れることすらなかった。では、この物語はいったい何だったのだろう?どうにもならない断絶だけなら、最初から見えているのだが。
『She lover』
マッチングアプリで出会った女ふたり。それぞれ、彼、夫というパートナーがいる。会話が進むにつれて、ふたりの関係性や心の揺れは見えて来る。ただ、男たちを無自覚でひどい人にしすぎない方が、女ふたりの、なぜパートナーから心が離れてお互いに惹かれていったのか、が描けたのでは。後半の、女たちそれぞれが内心を語るモノローグは、それまでの流れで十分伝わっている内容なので、説明しすぎかもしれない。
『クマといくら』
地元の町にずっと住むもの、外に出て行ったものが久しぶりに集まる序盤、人物の関係を理解するのが少し難しい。クマを駆除する=実は人を殺している、という事実の出し方がサラッとしすぎて、聞いた側のリアクションも薄い。大事件のはずなのだが。不妊治療と子ども殺し、クマの人権など、膨らみそうな話はでてくるのだが、思わせぶりに触るのみで発展や回収がされないまま終わってしまった。タイトルの「いくら」も印象がうすい。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

内藤裕敬
『或る町』
不条理劇として楽しく読んだ。展開もワクワクしたなあ。
そのワクワクが後半に行くにつれ、不条理的ワクワク感から外れて行った気がします。
そこに新しいオリジナリティを見つけようとなさっているのかな?
それが不条理を拡大できれば大賞だね。
『六畳間と女神様』
狂信的家族の物語。じわりと迫る、そのクレイジーさに書き訓れた作家であると感心した。
だが、何か足りない。信仰や信心の本質が歪んだ現代性に閉じ籠っちゃってる。作品の魅力も閉じ籠っちゃったかな。ラストまで笑える話だったらなあ、と思った。
『She lover』
密室での密会。二人の女性は、息苦しい交際を続けている。そんな秘密だらけに耐えられず、関係にヒビが入っていくのだが、その会話と言葉に作者の美意識も感じられ、ドキドキしながら読んだ。しかし、エンディングに近づくにつれ、作者が仕掛けた秘密だらけが実を結ばない。構造化が上手くいっていない。この物語で、秘密だらけが広く様々を暗喩すると思えただけに、もう少し、秘密を広く遊べたらなぁ、それ、読みたいね。
『クマといくら』
とても熱量を感じない会話で、人の命にかかわる物語が進行するのでドキリッとする。
そのドキリッが発展しない。続かない。これは、害獣としてのクマが、暗喩として面白く機能していないからじゃないのかな、と。後半になるにつれ、それを強く感じた。残念。
『杳たる月』
クリント・イーストウッドの「ミリオンダラーベイビー」「チェンジリング」この二作は、観終わって本当に辛かった。この作品もそう。けれど大きく違うのは、大きな嫌悪感を持ったまま読まされてしまうのだが、後味に実感が無い。私の中に傷が残らない。ただ嫌な感じが残るんだな。
どうしてくれるんだよ!そこが謎だけど、とにかく佳作!
----------------------------------------------------------------------------------------------
 宮田慶子
宮田慶子本年度の応募作品数は63作品、その中から最終選考に5作品が選ばれた。
『或る町』は、明らかに別役実作品に寄せて書かれているのだが、「コピー?」「オマージュ?」「パロディ?」という、作者自身の立ち位置が気になり、「なにを仕掛けているのか」という詮索の思いを強く持った。別役作品のような孤高の強力な文体を使うことへの作者の決意が問われる。結局、置かれていた荷物は自殺した男のもののようであるという“種明かし”や、“葛藤”の要素であるラジオが持ち去られる事により、ドラマは“整合性”に向かってしまう点が、別役作品との最も大きな違いであり同時に平板さを生んでしまったと言える。
『杳たる月』は、セリフの自然さや強さから浮かび上がる人物の魅力が、圧倒的に迫ってくる。義兄妹の関係や、殺人など、モラルでは語れない要素が重なり、そのまま崩壊へと向かっていく。当事者の内面への踏み込みが、距離のあるところから“犯罪の風景”を眺めている感があり、ラストの緊迫感がありながらも、それ以上にならないもどかしさを感じた。
『六畳間と女神様』は「カルト宗教」「宗教2世」などを扱いながら、根本である“人が信仰に求めるもの”の描き方に踏み込まないので、軸が見えてこない。兄弟の死と誕生のきっかけである震災の扱い方が曖昧で、残念ながら“ご都合主義的”に見えてしまう。創作の土台が掴みにくい。
『She lover』は登場人物それぞれの間に交わされる言葉がやや幼く、感情や思いや実感が伝わってこない。“女性同士のカップル”で尚且つ“バイ”であるという関係、その底にある“自分”を描きたいのだとしたら、語り合う言葉にこそ、作者の感性がしっかりと通っていてほしいと思う。男性像も非常にステレオタイプなので、全てが「あえて?」と探ったが、その作為や客観性は見出せなかった。
『クマといくら』は“クマ”の存在の捉え方と、同級生たちの関係と、時系列の飛躍がうまく噛み合っていない。メタファーとしてクマを捉えるのだとしたら、現実に“血を流して登場する一郎”“クマを捨てる”などが混乱を生む。さまざまな仕掛けが何に集約されていくのか掴みにくかった。
選考の結果、『杳たる月』が佳作になった。まずは圧倒的にオリジナルな会話と、人物造形の魅力が大きい。
全体に身近な世界の混沌を描いた作品が多かったが、身近でありながら、距離感のある、何かしら冷めた場所でその世界を眺めるといった作風が多いのも印象的だった。
戦場の報道が絶えない日々の中で、距離感としてしか描けない事に、今創作することのもどかしさを感じる今回の選考だった。