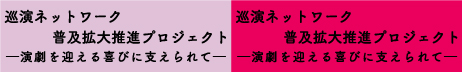『日本の劇』戯曲賞2020 最終選考委員選評
「日本の劇」戯曲賞2020(主催/文化庁・日本劇団協議会)の最終選考会が2020年10月8日、日本劇団協議会会議室にて行われ、次のとおりに決定しました。
最終選考委員の演出家は、板垣恭一、上村聡史、内藤裕敬、中屋敷法仁、宮田慶子の5氏(敬称略、五十音順)です。
なお、佳作として1作品を選出いたしました。
今年度の応募総数は46作品。一次選考を経て最終候補作品として選出されたのは、次の6作品でした。
池神泰三 『石棺 ((本当の記憶喪失!))』
長内 敬 『風に向かいて』
辻本久美子『遠きアカシア』
有吉朝子 『世界が私を嫌っても』
中田夢花 『墮生夢死スイセイムシ』
むつみあき『サクラのくせに、咲き誇る』
■【最終選考委員選評】■
 「困らせているものは何か」という考え方 板垣恭一
「困らせているものは何か」という考え方 板垣恭一
感染症が流行している中、たくさんの応募があったそうで嬉しいです。さて、今年は「困る」をキーワードに解説してみたいと思います。物語とは「困っている人を見せ、観客に己を省みてもらう遊び」ではないか、僕はそう考えています。
大切なのは「①=困る人」が誰で、「②=困らせているもの」は何かをしっかり描くことです。①がまず重要で、これが分からないと観客は物語そ
のものを見失います。そして②がさらに重要で、それは人とは限らず、モノや環境や状況であったりしますが、ちゃんと描けていないと深みのある物語にはなり得ないと考えています。戦争などを題材にすると、そこそこ何かを書いたような気になってしまいがちなのは、①が簡単にクリアできるからであり、同時に物語が深まらないことが多いのは、②において「戦争」以外についての掘り下げが甘いからではないでしょうか。ここ数年、応募作に「評伝」モノが多いですが、共通の欠点を持っているように感じます。①は評伝になるくらいだからハッキリしているけれど、②を具体的に描き切れていないという欠点です。
『世界が私を嫌っても』は台詞の躍動感を一番感じた作品でした。①は平林たい子をモデルとした主人公ですが、やはり②が不安定な印象。自分自身が②になっているはずと読みましたが仮説以上にはならず、佳作に一票。『サクラのくせに、咲き誇る』こちらも主人公自身が②であると思いますが、ラストシーンでそこにオチをつけてもらえず、自分自身の問題を時代のせいにして逃げちゃったみたいな印象。それ以外は結構好きだったので残念です。『遠きアカシア』は①が展開により都合よく変化してしまい読みづらく。②に戦争的なものを配置していますが、具体性を欠いていて消化不良。『墮生夢死』はやはり②の詰めが甘い印象。コロナ的なものや、共同体の限界が描かれ期待大でしが、それらがセンセーショナル以上の意味を持って整理されておらず、着地点があやふや。『石棺((本当の記憶喪失!))』①②ともにミステリアスなまま読ませてくれるもののその先に発見がなく。『風に向かいて』評伝として典型的な罠に陥ったかもしれません。主人公がなぜ理想を胸にラストまで立ち続けられるのか「なるほど」と思わせてくれる部分が描かれておらず。主人公が語る内容は素敵だけど、それだけでは演劇にはなり得ないというところを一考いただきたく。以上、今年の選評でした。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 誰に伝えたい戯曲なのか
誰に伝えたい戯曲なのか
上村聡史
“現代の作家が書いた現代の劇を”。戯曲賞の選
考にあたり、このようなテーマを判断基準にしている。同時代に生きる観客が、この時代に響く言葉を劇場で体験できることは、このうえない至福だ。故に評伝劇や歴史を扱った芝居であれば、なぜ今に、その時代や、その時代を生きた人物を描く必然性があるのか、そのあたりの現代へ投げかける強度こそが重要に思う。今年の戯曲賞は、例年より評伝劇のような題材が多かったが、だとしたら、自身の執筆活動が、興味や関心を超えて、誰に向け誰を感動させたいのか、または驚かせたいのか、ということにもっと探求してほしかった。加えて、戯曲は物語を構成するほかに、台詞を俳優が音にして観客に伝えるという行為まで含まれる形態であるため、黙読だけでは終わらない、“音”への意識を考えることも必要であろう。
佳作となった『世界が私を嫌っても』についていえば、台詞の躍動感、硬軟織り交ぜた語り口といった“音”に対しては、目を見張るものがあった。ただ私が気になったのは、なぜ1910~50年代とその時代に生きた人物を取り上げたかである。「頑なに自分の信念を守ること、そして葛藤」を今に投げかけたいのだとしたら、思想の弾圧と自由の獲得が渦巻く場にいた人間を、時代を取り上げることは内実に波及しない情報が入り込んでしまったし、逆にこの時代を取り上げたかったのなら、同時代に投げかける強度や深みがもっと欲しかった。現代劇という意味では『堕生夢死』が、小さなコミュニティ(家族・友人の集う場)が設定であり、開口第一番「おっぱい」という台詞から始まる、挑発的かついびつな世界観に面白さを感じた。しかし、描きたいことが多かったのか、人物たちの言動の裏打ちが弱く、リアリティーのない思わせぶりな印象で終わった。
『石棺((本当の記憶喪失!))』は小気味いい展開に心地よさがありつつもラストへの流れが甘い。『風に向かいて』は評伝劇でありながらも「ジャーナリズムと信念」という現代への投げかけはあるものの人物たちの色彩が足りない。『遠きアカシア』は最大の見せ場であろう別離への葛藤が表現として弱い。『サクラのくせに、咲き誇る』は、レンタル彼氏や披露宴友人代行といった実際のモチーフを入れ込みフィクションが現実を凌駕していく面白さがありつつも、書き手がモチーフに対し常に一定的なスタンスを取っていて意外性がなかった。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

内藤裕敬(南河内万歳一座)
『石棺((本当の記憶喪失!))』
モチーフ主義の作家だと思います。モチーフを遊びながら透けて見えるテーマさえも遊ぼうとしている。私は、その作業を期待しながら読めた。しかし、途中からテーマと構造の行方を見定められぬまま、迷いながらの後半になってしまった。可能性はあるのになあ…。
『風に向かいて』
昨今の公文書改ざん。新聞社の報道のあり方。忖度の密室性などなど。作者の強い思いを感じました。ジャーナリズムの有るべき姿勢が強烈なテーマとなっている。しかし、戯曲として読むと会話の中に文学性が薄い。劇的世界観を築こうという意志よりも、テーマの発表が優先されている。そう感じるのだ。テーマと共に、作者が戯曲、演劇にこだわった様々を作品の中で楽しみたい。
『遠きアカシア』
バイオリンの天才少女と、そのバイオリンを追い中国にまで広がる大作だ。家族、歴史、人生…と、スペクタクルに盛り込んだ。重要な役割を果たすのが消えたバイオリン。なのに、それを構造化する仕掛けが弱い。作品中、全ての不確かなものを代表するバイオリンが、読む側の内面へ刺さる暗喩とならないものか? 物語りが面白いだけに残念。
『堕生夢死』
台詞の感覚に良いものを持っている作家だと思う。会話に感性を感じる。なのに何故、賞に輝けなかったかだ。「ははァ、そうだったのか」がオチになっているからだ。そこから先が劇作家の勝負! 愛情、死、残された者達、その心を言葉にする為に格闘しなければならない。オチの先にこそ、あなたが書かなければならない世界があるはず。「ははァ、そうだったのか」で終わってはいけない。
『サクラのくせに、咲き誇る』
言葉と会話が、表層を滑って行く感じ。そこが、この作家の持ち味なのかも知れない。その向こう側にある登場人物の背景が決して具体的な言葉や会話にならない。踏み込んだことを言葉でやらない。それが、この作家の戦略だとするならば、本作では足りない。もっと徹底してソギ落とさねば。戦略でないならば、劇の世界観が弱いと思う。
『世界が私を嫌っても』
受賞作である。しかし佳作入選だった。おそらく書き慣れた方だ。これまでに複数の作品を仕上げてこられたと思う。とても、うまい。なのにどうして? 作者が、この作品で何をやろうとしたのか? 私は、そこに大きな期待を持って読んだ。何故、この評伝を書かねばならなかったのか? その部分が、いつ出て来るのかワクワクしていた。特にラスト。自らの生き方を貫いて来た主人公が、その人生で、一人の女性として他者と向き合わねばならなくなる。「やっと来たか!」ここで、この作者の言葉が聞けると思った。思想や意志だけでは太刀打ちできない人間関係を目の前に、心は何を叫び出すのか? そこに文学も生まれる。ここまで、この物語を書いて来た、この作家の勝負所だ。評伝を仕上げたという以上の作品になりきれていなかったと思えたんだなあ……。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

中屋敷法仁(柿喰う客)
最終選考に残った作品たちは、どれも異なる輝きを放っていた。しかし、残念ながら「演劇」として「劇場」で見たいと思わせる程の魅力を感じなかった。『石棺 ((本当の記憶喪失!)) 』は、興味深いイメージの連なりが独創的だった。しかし扱う主題があちこちに拡散し、後半になるにつれ作品のエネルギーが縮小している。最後の瞬間まで楽しみたかった。
『風に向かいて』は、ひとつの時代を丁寧に描き抜く胆力が見事。ジャーナリズムという主題は、現代の世相を生々しく反映していると感じた。問題となってくるのは言葉の軽やかさ。ひとつひとつの台詞が重く、流れが悪い。台詞が「俳優の声になる」ということを念頭に置き、ブラッシュアップが必要だ。
『遠きアカシア』は時代と空間を壮大なドラマを書こうという野心は素晴らしかった。ただ、細かい設定の粗が、作品の良さを阻害している。音楽家、そして楽器について、さらに深く取材すべきだ。
『墮生夢死』はおっぱいを巡る対話から、生と性に迫る展開が実に鮮やかだった。唯一無二の演劇作品になり得る要素を数多く備えていたが、クライマックスに至るにつれて、一般化されたモチーフが続き残念。「愛してる」「包丁を地面に落とす」など、劇的な瞬間を装っているとしか思えなかった。素晴らしい劇言語の感性を信じ、独自の世界を書き散らかしてほしい。
『サクラのくせに、咲き誇る』は、圧倒的に作者の体験が不足している。「花見」「チカドル」「BBQ」イメージがあまりにも空虚だ。何より代行スタッフへの捉え方が一義的で、劇進行の中で発展していかない。肉感のある言葉を耕してほしい。
戯曲として最も読みやすく、違和感を覚えなかったのは『世界が私を嫌っても』。劇構成の巧みさは応募作の中で突出していた。では何故、最優秀に推すことができなかったかと言えば、果たしてこの戯曲の上演を見たいかどうか、に尽きる。どこまでも「良い戯曲」という枠を抜き出さない。劇場をあっと言わせる、企みが足りない。総評としては、いずれの作品も「上演されること」、そして「観客がいること」への意識がまだまだ足りないと感じた。生み出してほしいのは、言葉や物語や人物ではない。それらが劇場空間で観客とともに、鮮やかに混ざり合う「日本の劇」なのだ。
----------------------------------------------------------------------------------------------
 物足りなさ・・・・・・ 宮田慶子(青年座)
物足りなさ・・・・・・ 宮田慶子(青年座)
2次選考に残った6作品は、作者の年代が十代から七十代までと幅広く、扱う題材も書き手の手法も様々で、その意味では“オリジナリティ”のある作品たちでした。どの戯曲も「なかなか上手いセリフ」が書けていますし、テンポもよく、時には「気の利いた蘊蓄」も織り込まれていたりで、ある意味「読みやすい」作品が多かった印象です。けれども、では、戯曲とはそういうものなのか、と考えると、ふと気持ちが立ち止まってしまうのが正直なところです。
例年この選評で書いてきている「会話を成立させる」「リズム感よく」「オリジナリティを」という点からは、どの作品もそれなりに意識されているようには思うのですが、何か物足りないのです。読み終わったときにどうしても、「で?」という問いかけをしてみたくなってしまうのです。
『石棺((本当の記憶喪失!))』は、男二人のやりとりが快調です。現代の「ゴドー」なのかと読んでいて期待が膨らみます。タイトルも気になります。石棺につめてしまったものが気になります。しかし、後半で女が登場してから、一気に作風も混沌とし、同時に世界が矮小化します。ついに最後は全てを説明するト書きになって終わります。結局、観念に連れて行かれただけになってしまいます。
『風に向かいて』は、近代ジャーナリズムの先駆者である陸羯南の評伝劇の形になっており、足跡を丁寧に辿りながら戯曲に仕立てた労作なのですが、評伝劇の落とし穴ともいえる「時系列の全て」を大切にしすぎて、焦点がはっきりしません。ドラマの起伏を生み出す「突き放す視点」が必要かもしれません。「新聞を作り始める」ところから始めるとか、「近代明治の中を生きた津軽人としての不屈の精神」などの視点もあるかと思います。
『遠きアカシア』。情報や裏付けのための台詞が多く、人物が「理由」で成り立っているように思います。そのために、大連にまで広がる大きな設定を作りながら、人間たちの生きたドラマが立ち上がってきません。「本物を求める旅」が主題であるのに、おそらく上演時には演奏が「吹き替え」「録音音源」でなければ成立しない矛盾点があるので、テレビドラマ的題材のように思います。
『墜生夢死』は、一人の男の死をめぐる一人一人の関わり方の違いが明確に書き分けられるともっと立体的な作りになると思います。要となる妹も、単なる曖昧な“雰囲気もの”になってしまっています。
『サクラのくせに、咲き誇る』は、フェイクな存在のまま偽名で暮らす主人公の、乾いた失望感が面白く、台詞の展開もスリリングです。ラストの着地点が物足りない気がします。心の奥をもう少し覗き込んでみたいです。
結果、『世界が私を嫌っても』が佳作となりました。評伝を題材としていますが、主人公の強烈な個性や、簡潔な台詞、叙情溢れる場面設定がうまく絡み合って、独自の世界観を作っています。それでもやはり、場面構成の絞り込みが必要かと思います。特に戦後の描き方に客観的な視点が必要に思います。
「この題材を書きたかった想いの芯」が届いてきて欲しいと願います。
今後も「上演」につながる戯曲賞として、多くの方に目指していただければありがたいです。
「日本の劇」戯曲賞2020(主催/文化庁・日本劇団協議会)の最終選考会が2020年10月8日、日本劇団協議会会議室にて行われ、次のとおりに決定しました。
最終選考委員の演出家は、板垣恭一、上村聡史、内藤裕敬、中屋敷法仁、宮田慶子の5氏(敬称略、五十音順)です。
【最優秀賞】 該当なし
なお、佳作として1作品を選出いたしました。
【佳作】 有吉朝子 『世界が私を嫌っても』
今年度の応募総数は46作品。一次選考を経て最終候補作品として選出されたのは、次の6作品でした。
【最終候補作品】(受付番号順)
池神泰三 『石棺 ((本当の記憶喪失!))』
長内 敬 『風に向かいて』
辻本久美子『遠きアカシア』
有吉朝子 『世界が私を嫌っても』
中田夢花 『墮生夢死スイセイムシ』
むつみあき『サクラのくせに、咲き誇る』
■【最終選考委員選評】■
 「困らせているものは何か」という考え方 板垣恭一
「困らせているものは何か」という考え方 板垣恭一感染症が流行している中、たくさんの応募があったそうで嬉しいです。さて、今年は「困る」をキーワードに解説してみたいと思います。物語とは「困っている人を見せ、観客に己を省みてもらう遊び」ではないか、僕はそう考えています。
大切なのは「①=困る人」が誰で、「②=困らせているもの」は何かをしっかり描くことです。①がまず重要で、これが分からないと観客は物語そ
のものを見失います。そして②がさらに重要で、それは人とは限らず、モノや環境や状況であったりしますが、ちゃんと描けていないと深みのある物語にはなり得ないと考えています。戦争などを題材にすると、そこそこ何かを書いたような気になってしまいがちなのは、①が簡単にクリアできるからであり、同時に物語が深まらないことが多いのは、②において「戦争」以外についての掘り下げが甘いからではないでしょうか。ここ数年、応募作に「評伝」モノが多いですが、共通の欠点を持っているように感じます。①は評伝になるくらいだからハッキリしているけれど、②を具体的に描き切れていないという欠点です。
『世界が私を嫌っても』は台詞の躍動感を一番感じた作品でした。①は平林たい子をモデルとした主人公ですが、やはり②が不安定な印象。自分自身が②になっているはずと読みましたが仮説以上にはならず、佳作に一票。『サクラのくせに、咲き誇る』こちらも主人公自身が②であると思いますが、ラストシーンでそこにオチをつけてもらえず、自分自身の問題を時代のせいにして逃げちゃったみたいな印象。それ以外は結構好きだったので残念です。『遠きアカシア』は①が展開により都合よく変化してしまい読みづらく。②に戦争的なものを配置していますが、具体性を欠いていて消化不良。『墮生夢死』はやはり②の詰めが甘い印象。コロナ的なものや、共同体の限界が描かれ期待大でしが、それらがセンセーショナル以上の意味を持って整理されておらず、着地点があやふや。『石棺((本当の記憶喪失!))』①②ともにミステリアスなまま読ませてくれるもののその先に発見がなく。『風に向かいて』評伝として典型的な罠に陥ったかもしれません。主人公がなぜ理想を胸にラストまで立ち続けられるのか「なるほど」と思わせてくれる部分が描かれておらず。主人公が語る内容は素敵だけど、それだけでは演劇にはなり得ないというところを一考いただきたく。以上、今年の選評でした。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 誰に伝えたい戯曲なのか
誰に伝えたい戯曲なのか上村聡史
“現代の作家が書いた現代の劇を”。戯曲賞の選
考にあたり、このようなテーマを判断基準にしている。同時代に生きる観客が、この時代に響く言葉を劇場で体験できることは、このうえない至福だ。故に評伝劇や歴史を扱った芝居であれば、なぜ今に、その時代や、その時代を生きた人物を描く必然性があるのか、そのあたりの現代へ投げかける強度こそが重要に思う。今年の戯曲賞は、例年より評伝劇のような題材が多かったが、だとしたら、自身の執筆活動が、興味や関心を超えて、誰に向け誰を感動させたいのか、または驚かせたいのか、ということにもっと探求してほしかった。加えて、戯曲は物語を構成するほかに、台詞を俳優が音にして観客に伝えるという行為まで含まれる形態であるため、黙読だけでは終わらない、“音”への意識を考えることも必要であろう。
佳作となった『世界が私を嫌っても』についていえば、台詞の躍動感、硬軟織り交ぜた語り口といった“音”に対しては、目を見張るものがあった。ただ私が気になったのは、なぜ1910~50年代とその時代に生きた人物を取り上げたかである。「頑なに自分の信念を守ること、そして葛藤」を今に投げかけたいのだとしたら、思想の弾圧と自由の獲得が渦巻く場にいた人間を、時代を取り上げることは内実に波及しない情報が入り込んでしまったし、逆にこの時代を取り上げたかったのなら、同時代に投げかける強度や深みがもっと欲しかった。現代劇という意味では『堕生夢死』が、小さなコミュニティ(家族・友人の集う場)が設定であり、開口第一番「おっぱい」という台詞から始まる、挑発的かついびつな世界観に面白さを感じた。しかし、描きたいことが多かったのか、人物たちの言動の裏打ちが弱く、リアリティーのない思わせぶりな印象で終わった。
『石棺((本当の記憶喪失!))』は小気味いい展開に心地よさがありつつもラストへの流れが甘い。『風に向かいて』は評伝劇でありながらも「ジャーナリズムと信念」という現代への投げかけはあるものの人物たちの色彩が足りない。『遠きアカシア』は最大の見せ場であろう別離への葛藤が表現として弱い。『サクラのくせに、咲き誇る』は、レンタル彼氏や披露宴友人代行といった実際のモチーフを入れ込みフィクションが現実を凌駕していく面白さがありつつも、書き手がモチーフに対し常に一定的なスタンスを取っていて意外性がなかった。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

内藤裕敬(南河内万歳一座)
『石棺((本当の記憶喪失!))』
モチーフ主義の作家だと思います。モチーフを遊びながら透けて見えるテーマさえも遊ぼうとしている。私は、その作業を期待しながら読めた。しかし、途中からテーマと構造の行方を見定められぬまま、迷いながらの後半になってしまった。可能性はあるのになあ…。
『風に向かいて』
昨今の公文書改ざん。新聞社の報道のあり方。忖度の密室性などなど。作者の強い思いを感じました。ジャーナリズムの有るべき姿勢が強烈なテーマとなっている。しかし、戯曲として読むと会話の中に文学性が薄い。劇的世界観を築こうという意志よりも、テーマの発表が優先されている。そう感じるのだ。テーマと共に、作者が戯曲、演劇にこだわった様々を作品の中で楽しみたい。
『遠きアカシア』
バイオリンの天才少女と、そのバイオリンを追い中国にまで広がる大作だ。家族、歴史、人生…と、スペクタクルに盛り込んだ。重要な役割を果たすのが消えたバイオリン。なのに、それを構造化する仕掛けが弱い。作品中、全ての不確かなものを代表するバイオリンが、読む側の内面へ刺さる暗喩とならないものか? 物語りが面白いだけに残念。
『堕生夢死』
台詞の感覚に良いものを持っている作家だと思う。会話に感性を感じる。なのに何故、賞に輝けなかったかだ。「ははァ、そうだったのか」がオチになっているからだ。そこから先が劇作家の勝負! 愛情、死、残された者達、その心を言葉にする為に格闘しなければならない。オチの先にこそ、あなたが書かなければならない世界があるはず。「ははァ、そうだったのか」で終わってはいけない。
『サクラのくせに、咲き誇る』
言葉と会話が、表層を滑って行く感じ。そこが、この作家の持ち味なのかも知れない。その向こう側にある登場人物の背景が決して具体的な言葉や会話にならない。踏み込んだことを言葉でやらない。それが、この作家の戦略だとするならば、本作では足りない。もっと徹底してソギ落とさねば。戦略でないならば、劇の世界観が弱いと思う。
『世界が私を嫌っても』
受賞作である。しかし佳作入選だった。おそらく書き慣れた方だ。これまでに複数の作品を仕上げてこられたと思う。とても、うまい。なのにどうして? 作者が、この作品で何をやろうとしたのか? 私は、そこに大きな期待を持って読んだ。何故、この評伝を書かねばならなかったのか? その部分が、いつ出て来るのかワクワクしていた。特にラスト。自らの生き方を貫いて来た主人公が、その人生で、一人の女性として他者と向き合わねばならなくなる。「やっと来たか!」ここで、この作者の言葉が聞けると思った。思想や意志だけでは太刀打ちできない人間関係を目の前に、心は何を叫び出すのか? そこに文学も生まれる。ここまで、この物語を書いて来た、この作家の勝負所だ。評伝を仕上げたという以上の作品になりきれていなかったと思えたんだなあ……。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

中屋敷法仁(柿喰う客)
最終選考に残った作品たちは、どれも異なる輝きを放っていた。しかし、残念ながら「演劇」として「劇場」で見たいと思わせる程の魅力を感じなかった。『石棺 ((本当の記憶喪失!)) 』は、興味深いイメージの連なりが独創的だった。しかし扱う主題があちこちに拡散し、後半になるにつれ作品のエネルギーが縮小している。最後の瞬間まで楽しみたかった。
『風に向かいて』は、ひとつの時代を丁寧に描き抜く胆力が見事。ジャーナリズムという主題は、現代の世相を生々しく反映していると感じた。問題となってくるのは言葉の軽やかさ。ひとつひとつの台詞が重く、流れが悪い。台詞が「俳優の声になる」ということを念頭に置き、ブラッシュアップが必要だ。
『遠きアカシア』は時代と空間を壮大なドラマを書こうという野心は素晴らしかった。ただ、細かい設定の粗が、作品の良さを阻害している。音楽家、そして楽器について、さらに深く取材すべきだ。
『墮生夢死』はおっぱいを巡る対話から、生と性に迫る展開が実に鮮やかだった。唯一無二の演劇作品になり得る要素を数多く備えていたが、クライマックスに至るにつれて、一般化されたモチーフが続き残念。「愛してる」「包丁を地面に落とす」など、劇的な瞬間を装っているとしか思えなかった。素晴らしい劇言語の感性を信じ、独自の世界を書き散らかしてほしい。
『サクラのくせに、咲き誇る』は、圧倒的に作者の体験が不足している。「花見」「チカドル」「BBQ」イメージがあまりにも空虚だ。何より代行スタッフへの捉え方が一義的で、劇進行の中で発展していかない。肉感のある言葉を耕してほしい。
戯曲として最も読みやすく、違和感を覚えなかったのは『世界が私を嫌っても』。劇構成の巧みさは応募作の中で突出していた。では何故、最優秀に推すことができなかったかと言えば、果たしてこの戯曲の上演を見たいかどうか、に尽きる。どこまでも「良い戯曲」という枠を抜き出さない。劇場をあっと言わせる、企みが足りない。総評としては、いずれの作品も「上演されること」、そして「観客がいること」への意識がまだまだ足りないと感じた。生み出してほしいのは、言葉や物語や人物ではない。それらが劇場空間で観客とともに、鮮やかに混ざり合う「日本の劇」なのだ。
----------------------------------------------------------------------------------------------
 物足りなさ・・・・・・ 宮田慶子(青年座)
物足りなさ・・・・・・ 宮田慶子(青年座)2次選考に残った6作品は、作者の年代が十代から七十代までと幅広く、扱う題材も書き手の手法も様々で、その意味では“オリジナリティ”のある作品たちでした。どの戯曲も「なかなか上手いセリフ」が書けていますし、テンポもよく、時には「気の利いた蘊蓄」も織り込まれていたりで、ある意味「読みやすい」作品が多かった印象です。けれども、では、戯曲とはそういうものなのか、と考えると、ふと気持ちが立ち止まってしまうのが正直なところです。
例年この選評で書いてきている「会話を成立させる」「リズム感よく」「オリジナリティを」という点からは、どの作品もそれなりに意識されているようには思うのですが、何か物足りないのです。読み終わったときにどうしても、「で?」という問いかけをしてみたくなってしまうのです。
『石棺((本当の記憶喪失!))』は、男二人のやりとりが快調です。現代の「ゴドー」なのかと読んでいて期待が膨らみます。タイトルも気になります。石棺につめてしまったものが気になります。しかし、後半で女が登場してから、一気に作風も混沌とし、同時に世界が矮小化します。ついに最後は全てを説明するト書きになって終わります。結局、観念に連れて行かれただけになってしまいます。
『風に向かいて』は、近代ジャーナリズムの先駆者である陸羯南の評伝劇の形になっており、足跡を丁寧に辿りながら戯曲に仕立てた労作なのですが、評伝劇の落とし穴ともいえる「時系列の全て」を大切にしすぎて、焦点がはっきりしません。ドラマの起伏を生み出す「突き放す視点」が必要かもしれません。「新聞を作り始める」ところから始めるとか、「近代明治の中を生きた津軽人としての不屈の精神」などの視点もあるかと思います。
『遠きアカシア』。情報や裏付けのための台詞が多く、人物が「理由」で成り立っているように思います。そのために、大連にまで広がる大きな設定を作りながら、人間たちの生きたドラマが立ち上がってきません。「本物を求める旅」が主題であるのに、おそらく上演時には演奏が「吹き替え」「録音音源」でなければ成立しない矛盾点があるので、テレビドラマ的題材のように思います。
『墜生夢死』は、一人の男の死をめぐる一人一人の関わり方の違いが明確に書き分けられるともっと立体的な作りになると思います。要となる妹も、単なる曖昧な“雰囲気もの”になってしまっています。
『サクラのくせに、咲き誇る』は、フェイクな存在のまま偽名で暮らす主人公の、乾いた失望感が面白く、台詞の展開もスリリングです。ラストの着地点が物足りない気がします。心の奥をもう少し覗き込んでみたいです。
結果、『世界が私を嫌っても』が佳作となりました。評伝を題材としていますが、主人公の強烈な個性や、簡潔な台詞、叙情溢れる場面設定がうまく絡み合って、独自の世界観を作っています。それでもやはり、場面構成の絞り込みが必要かと思います。特に戦後の描き方に客観的な視点が必要に思います。
「この題材を書きたかった想いの芯」が届いてきて欲しいと願います。
今後も「上演」につながる戯曲賞として、多くの方に目指していただければありがたいです。
----------------------------------------------------------
文化庁委託事業「令和2年度次代の文化を創造する新進芸術家育成事業」
日本の演劇人を育てるプロジェクト 制作:公益社団法人日本劇団協議会
文化庁委託事業「令和2年度次代の文化を創造する新進芸術家育成事業」
日本の演劇人を育てるプロジェクト 制作:公益社団法人日本劇団協議会