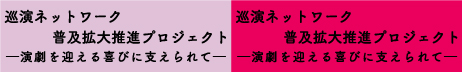『日本の劇』戯曲賞2017 最終選考委員選評

「日本の劇」戯曲賞2017(主催/文化庁・日本劇団協議会)の最終選考会が2017年9月22日、日本劇団協議会会議室にて行われ次の通りに決定しました。
最終選考委員の演出家は板垣恭一、上村聡史、内藤裕敬、中屋敷法仁、宮田慶子の5氏(敬称略、五十音順)です。
最優秀賞 該当なし
なお、佳作として2作品を選出いたしました。
佳作 「桜の秋」 辻本久美子
「空谷の湧水」 ほしのしんや
なお、今年度の応募総数は51作品。一次選考を経て最終候補作品として選出されたのは、次の5作品でした。
【最終候補作品】(受付番号順)
「バベルの塔」 小宮英嗣
「桜の秋」 辻本久美子
「空谷の湧水」 ほしのしんや
「想いはレンズを通って ~ハリーと呼ばれたカメラマン~」 相馬聡廣
「ミュージカル こんにちは 赤ちゃん」 白木利和
■【最終選考委員選評】■
 技術は学べるものです/板垣恭一
技術は学べるものです/板垣恭一
戯曲を読む時、二つの点に着目します。「①テーマ=何を描いているのか」と、「②技術=どう書いているのか」です。今回読んだ応募作(下読み10作+最終選考5作)では②をクリアする方がとても少なかったです。ちなみに「②はダメだが①が優れている」という戯曲に出会ったことがありません。①は「作家の人生観」だとも思うのでともかく、②はその気になれば習得できるはずなので歯がゆく感じています。
選評です。
『バベルの塔』はこの戯曲選考会をモデルにしたもので、冒険は少ないですが②はクリアしています。となると①を期待するのですが「選考委員は謙虚になれ」的なことに着地しており、困ってしまいました。「何を描きたいか」は、すなわち「なぜ書くのか」だと思います。「なぜこの作品を書くの?」という疑問が大いに残る作品でした。
『想いはレンズを通って~ハリーと呼ばれたカメラマン~』は、評伝をそのまま起こしたような作品でした。弱点は「物語」について無頓着である点。人の営みを時系列で並べても物語にはなりません。
『こんにちは赤ちゃん』は、ミュージカル台本の典型的な失敗例です。セリフで語った情報を、直後に歌で語られるのは退屈で苦痛です。
『桜の秋』は設定に偶然が多い物語でした。御都合主義は、ある程度OK派ですが、ちょっと多すぎです。「時空を越えての親子の再会」は一見良い話風ですが、この物語の設定を重ねると全然良い話じゃないとも思いました。
『空谷の湧水』は唯一②をしっかりクリアしていました。ただ①に当たる部分に面白みが感じられず。例えると、手間暇かけた立派な料理だけど味は普通、みたいな作品でした。以上、今回はあえてメッタ斬りさせていただきました。佳作の作者にはお会い出来るそうなので、色々お話ししたいと思います。
物語には「基本的なルール」があり、それに伴う「技術」もあります。例えば僕は市販の「映画脚本術」的な本を読みました。小説、神話、民話、音楽、マンガ、ゲームなどの分析本も参考にしています。みなさんの創作が実り多いものになるようお祈り申し上げます。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 “現代”に戯曲を書くということ
“現代”に戯曲を書くということ
/上村聡史(文学座)
“戯曲”という呼称は、“台本”と比較して、いささか大仰というか、文芸の香りが漂う語感がする。人が声を出して、どのように物語を響かせるかという観点から見れば、さほど変わりはない。ただ“台本”の方が、上演する際の劇場や予算、キャストの人数といった条件が反映されていて、これくらいの違いなのかもしれない。しかし、書き手は、戯曲を書ことと台本を書くことは、大きく異なる。台本を書くことが前述したように劇場条件や出演するメンバーの数やキャラクターなどの実際的なことが考慮されるとしたら、戯曲はその作家の志向性、批評性を何よりも優先していかなければならない。また“現代”に向けて、今までの戯曲にはないような劇構造や人物関係のやり取り、劇的効果を生むような作劇に挑戦しなくてはならない。ただ、それも新しいことだけを展開するのではなく、メタファーを含めた物語を構成し、観客や読者と共鳴できる想像性を持たなくてはならない。
そのような意味で、今回の審査で最優秀賞を出さなかったのは、この「戯曲を書く」ということに対しての意識が全体の候補作品を含め、低く感じたからだ。
佳作となった『桜の秋』でいえば、展開やテーマ性は大変刺激的ながらも、人間と人間が抱える想いや感情を温かな視点で捉えたバランスは巧みだったものの、幽霊を登場させる際の約束ごとや電話口から聞こえてくる声の処理が、ご都合的で平均点以下のように感じ、せっかくの高評価部分がかすんで見えてしまった。
また、もう一つの佳作『空谷の湧水』は、人物設定と状況、そして関係性を深く掘り下げて紡いだ台詞のやり取りが、俳優の演技への信頼も含めた新しい文体であり、そのことはとても目を見張るものを感じた。だが、それ故に展開するエピソードを掴むのが非常に難解で、結果、一番大事な作品の本質の提示がなかったように思えた。これは読者の想像の自由にという意見もあるかもしれないが、厳しいこと言えば、想像の自由に至るまでのエピソードに劇的な高揚感を覚えることはなかった。
『バベルの塔』は、議論劇の体裁を取りながらも、各人物の描写が、要となる言葉の選択や言葉遣いにまで至ってなかった。
『想いはレンズを通って~ハリーと呼ばれたカメラマン~』はドキュメントドラマの体裁をとりながら、一代記から透けて見えてこなくてならない、時代や人間関係の批評性を読み取れなかった。
『こんにちは 赤ちゃん』はミュージカルという体裁をとりながら、歌詞パートがシーンの心情説明に終わっていたため、世界観のクオリティを感じなかった。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

内藤裕敬(南河内万歳一座)
『バベルの塔』は、根気良く書いていらっしゃる。後半は、もう根気だけで書いている。根性がある。しかし、何故、後半を根気と根性で書かねばならなくなったのか? 戯曲賞の審査を題材にした物語だが、その内容が、20代の劇団員が、安居酒屋でボヤいている域を出ていないからだ。どうせなら、もっとメチャメチャな演劇批判に根気と根性を使うべきだ。「言われなくても、わかっている」そう思いながら読んじゃったよ。
『桜の秋』。作者は、何本もの作品を書いているのだろう。モチーフを遊び、広げて楽しむことを知っている。その中で、劇構造を、どう組み立てようか? それも遊んでいる。しかし、それ等が少しずつ甘い。おお! ここから演劇的になるのかな!? と思った所から、テレビドラマ的な、わかりやすさへ逃げてしまっている。ユウレイが便利に使われて、オレオレ詐欺の青年が、実はユウレイの息子だったというのがいらない。息子なのか? 息子かも知れない? 息子だったらどうしよう? その程度で良かったじゃないかなあ。とは言え、私は好きですね。この作風。
『空谷の湧水』はよく書けていると思いました。ちゃんと台詞になっている。戯曲とは、書くことで書かないことを表現しなければならない。書かないことで、より多くを表現できないかにチャレンジせねばならない。この作家は、それを心得ている。しかし、それだけではダメだ。どうも設計図通りに構成されている。壊す作業が無い。飛躍しなればならないことはないが、面白い発展が無ければ、登場人物が粛々とその役割りを記号的に持ち込んで来るだけだ。楽しめないチェーホフみたいになる。そこに自覚的となれば、相当な作品をお書きになるんじゃないのかな。期待しています。
『思いはレンズを通って~ハリーと呼ばれたカメラマン~』は、戦中、戦後を生きた一人のカメラマンの伝記だ。この方は、戯曲にチャレンジして日が浅いのだろうと思いながら読んだ。台詞に面白味と力が無い。個人史をなぞるように物語が進む。ならば、伝記そのものを読んだ方が良い。書く前から、どの言葉にこだわるかを決めてかかっている。どの場面の会話も色が変わらない。あるキャラクターと言葉たちに閉じ込められてしまっている。そうすると、登場人物が生き生きとしてこない。けれど、相当の熱意を持って、この作品に取り組んだことは読みとれた。書き続けて下さい。
『ミュージカル こんにちは赤ちゃん』はおそらく、女と男、仕事と子育て。それが、作者の身近なテーマなのだろう。そこからの出発は大変よろしい。しかし、それを叙事的に展開するのなら、ポイントで叙情が生きて来るだろう。物語が、現実の表層をすべって行く。その分、わかりやすいが奥行きが見えない。会話の後に歌。それも、会話の内面を歌で吐露するくり返しになっている。会話で何をやり、歌で何をやるのか? そこの専門性に欠ける。そこさえ踏み込めば、メリハリのある作品となったろう。可能性のあるテーマと物語だけに、そこが残念ですよ。
今回、最終候補作は5作品。どんなに少なく見積っても、このうち3作品を、私だったら最終候補に残さない。これが残るのであれば、私が下読みした中に最終まで残しても良い作品が何作かあった。確かに力作、野心作が数多く応募される。その中から台詞と会話を生きている何者かが語っているかどうか? 作者の中の困難が、物語をキリリとさせているかどうか? しっかりと選考すべきだと思いました。来年に期待します。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 中屋敷法仁(柿喰う客)
中屋敷法仁(柿喰う客)
異なる価値観が混ざり合い、様々な諸問題を抱える現代の「日本」。この複雑な題材に対し、どのような視点をもって描いたか。そして「日本」の観客の前で上演すべき作品なのか。そのふたつに重点をおいて審査を担当した。今回も数多くの未発表戯曲が集まったが、残念ながらどの作品も「最優秀賞」受賞という結論には至らなかった。
『空谷の湧水』は比較的よく書けており、人物描写や物語の展開が巧みであったことは否定しない。しかし果たしてこの戯曲が、劇場という空間で、俳優の身体を使って上演すべきものなのか、という疑問が残った。描かれる内容はオーソドックスなものであり、驚きや面白みに欠けていた。
その点では『桜の秋』は演劇としての企みに満ちており、上演されるのが楽しみになるものだった。ただ、劇中に仕掛けられたトリックやギミックの細かい調整が稚拙で、舞台作品として上演することは難しく感じた。この2作品が特別に「佳作」の受賞となったのは、それでも今後の可能性を感じられたからだ。
『想いはレンズを通って~ハリーと呼ばれたカメラマン~』は、劇世界は丁寧に描いてはいるが、ストーリーの展開、それを支える会話のやりとりがあまりにも単調だった。舞台作品の脚本としての密度が足りなかった。
『ミュージカル こんにちは赤ちゃん』はミュージカルという形式をとる必然性、即ち、なぜこの言葉をメロディに乗せるかが最後までわからなかった。労働、結婚、出産という諸問題も扱い切れていない。
『バベルの塔』はシチュエーションこそ期待させるものだったが、人物にも会話にも全く魅力がない。作家のワンアイディアで終わってしまっていた。最終候補作品は総じて、戯曲としての体裁を整えているだけの印象で、社会や時代を挑発するような野心を感じられなかった。劇場という小さな空間から世界を描き出す、そんな魔力をもった傑作と出会いたかった。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 宮田慶子(青年座)
宮田慶子(青年座)
全51作品の中から、最終選考には5作品が残り、結果的には、残念ながら優秀賞の該当作品はなく、「佳作2作品」という結果になった。
題材への執着や切り口の明確さ、人物設定や全体構成やセリフの言葉選びなどの技術面も含め、バランスよく高いレベルに届くのはなかなか困難なことである。
曖昧なシーンの設定が、全体を間の抜けた印象にも、身勝手な表現にも見せたりする。たった一言、たった一つの仕草で、観客の理解をミスリードすることもある。
大胆かつ慎重に、幕開きから終わりまで書き貫く“タフさ”を持って欲しい。
『バベルの塔』は、 “審査”に対する作者の考え方が見えない。審査に当たる「劇作家」たちも、審査会で交わされる言葉も、稚拙すぎて現実味がなく、何を揶揄しようとしているのかわからない。題材に対する劇作家の誠意として、しっかりとした姿勢を持つべきだ。
『想いはレンズを通って〜ハリーと呼ばれたカメラマン〜』は、基本的には“脚色”に当たるだろう。原作に対する敬意は感じられるが、それに添いすぎていて、劇作家としての視点が弱い。客観の役割の新聞記者が単なる「讃美者」になっている点が、ドラマを平板にしている。背後にある激動の時代との重ね合わせが曖昧で、一代記の広がりがない。
『ミュージカル こんにちは 赤ちゃん』は、あえてミュージカルにする意味はあったのだろうか。「仕事と育児の両立」「女性の人生選択」という題材に深く切り込めずに、“出来事”を追うだけの展開になっている。セリフと歌詞内容が重複するので、ドラマが停滞する。もっと飛躍があっても良いのかもしれない。
佳作となった『桜の秋』は、盛りだくさんなモチーフを持ち込んで、青春時代の夢を軸にした二人の女性の人生模様をエンターテイメントに仕立てた。幽霊に法則がなくご都合主義になったり、全てを因果付けしようとする無理がある。幽霊に使命や目的を持たせると、芯ができるかもしれない。
『空谷の湧水』は、台詞に生活の中の言葉としての“癖”があり、独特の空気感を生んではいるが、人物相互の距離感が掴みにくい。精神的に追い込まれた女性、過去を避けて生きる男、福島や処分場など、「疲弊した現代」と「湧水」との関係が明確になりたい。
戯曲は、演劇におけるすべての舞台表現の“土台”だ。
だからこそ、緻密な計算、言葉へのセンス、客観性のある推敲能力と、首尾一貫した作者の思いに支えられた、信頼の拠り所となる戯曲を期待する。

「日本の劇」戯曲賞2017(主催/文化庁・日本劇団協議会)の最終選考会が2017年9月22日、日本劇団協議会会議室にて行われ次の通りに決定しました。
最終選考委員の演出家は板垣恭一、上村聡史、内藤裕敬、中屋敷法仁、宮田慶子の5氏(敬称略、五十音順)です。
最優秀賞 該当なし
なお、佳作として2作品を選出いたしました。
佳作 「桜の秋」 辻本久美子
「空谷の湧水」 ほしのしんや
なお、今年度の応募総数は51作品。一次選考を経て最終候補作品として選出されたのは、次の5作品でした。
【最終候補作品】(受付番号順)
「バベルの塔」 小宮英嗣
「桜の秋」 辻本久美子
「空谷の湧水」 ほしのしんや
「想いはレンズを通って ~ハリーと呼ばれたカメラマン~」 相馬聡廣
「ミュージカル こんにちは 赤ちゃん」 白木利和
■【最終選考委員選評】■
 技術は学べるものです/板垣恭一
技術は学べるものです/板垣恭一戯曲を読む時、二つの点に着目します。「①テーマ=何を描いているのか」と、「②技術=どう書いているのか」です。今回読んだ応募作(下読み10作+最終選考5作)では②をクリアする方がとても少なかったです。ちなみに「②はダメだが①が優れている」という戯曲に出会ったことがありません。①は「作家の人生観」だとも思うのでともかく、②はその気になれば習得できるはずなので歯がゆく感じています。
選評です。
『バベルの塔』はこの戯曲選考会をモデルにしたもので、冒険は少ないですが②はクリアしています。となると①を期待するのですが「選考委員は謙虚になれ」的なことに着地しており、困ってしまいました。「何を描きたいか」は、すなわち「なぜ書くのか」だと思います。「なぜこの作品を書くの?」という疑問が大いに残る作品でした。
『想いはレンズを通って~ハリーと呼ばれたカメラマン~』は、評伝をそのまま起こしたような作品でした。弱点は「物語」について無頓着である点。人の営みを時系列で並べても物語にはなりません。
『こんにちは赤ちゃん』は、ミュージカル台本の典型的な失敗例です。セリフで語った情報を、直後に歌で語られるのは退屈で苦痛です。
『桜の秋』は設定に偶然が多い物語でした。御都合主義は、ある程度OK派ですが、ちょっと多すぎです。「時空を越えての親子の再会」は一見良い話風ですが、この物語の設定を重ねると全然良い話じゃないとも思いました。
『空谷の湧水』は唯一②をしっかりクリアしていました。ただ①に当たる部分に面白みが感じられず。例えると、手間暇かけた立派な料理だけど味は普通、みたいな作品でした。以上、今回はあえてメッタ斬りさせていただきました。佳作の作者にはお会い出来るそうなので、色々お話ししたいと思います。
物語には「基本的なルール」があり、それに伴う「技術」もあります。例えば僕は市販の「映画脚本術」的な本を読みました。小説、神話、民話、音楽、マンガ、ゲームなどの分析本も参考にしています。みなさんの創作が実り多いものになるようお祈り申し上げます。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 “現代”に戯曲を書くということ
“現代”に戯曲を書くということ/上村聡史(文学座)
“戯曲”という呼称は、“台本”と比較して、いささか大仰というか、文芸の香りが漂う語感がする。人が声を出して、どのように物語を響かせるかという観点から見れば、さほど変わりはない。ただ“台本”の方が、上演する際の劇場や予算、キャストの人数といった条件が反映されていて、これくらいの違いなのかもしれない。しかし、書き手は、戯曲を書ことと台本を書くことは、大きく異なる。台本を書くことが前述したように劇場条件や出演するメンバーの数やキャラクターなどの実際的なことが考慮されるとしたら、戯曲はその作家の志向性、批評性を何よりも優先していかなければならない。また“現代”に向けて、今までの戯曲にはないような劇構造や人物関係のやり取り、劇的効果を生むような作劇に挑戦しなくてはならない。ただ、それも新しいことだけを展開するのではなく、メタファーを含めた物語を構成し、観客や読者と共鳴できる想像性を持たなくてはならない。
そのような意味で、今回の審査で最優秀賞を出さなかったのは、この「戯曲を書く」ということに対しての意識が全体の候補作品を含め、低く感じたからだ。
佳作となった『桜の秋』でいえば、展開やテーマ性は大変刺激的ながらも、人間と人間が抱える想いや感情を温かな視点で捉えたバランスは巧みだったものの、幽霊を登場させる際の約束ごとや電話口から聞こえてくる声の処理が、ご都合的で平均点以下のように感じ、せっかくの高評価部分がかすんで見えてしまった。
また、もう一つの佳作『空谷の湧水』は、人物設定と状況、そして関係性を深く掘り下げて紡いだ台詞のやり取りが、俳優の演技への信頼も含めた新しい文体であり、そのことはとても目を見張るものを感じた。だが、それ故に展開するエピソードを掴むのが非常に難解で、結果、一番大事な作品の本質の提示がなかったように思えた。これは読者の想像の自由にという意見もあるかもしれないが、厳しいこと言えば、想像の自由に至るまでのエピソードに劇的な高揚感を覚えることはなかった。
『バベルの塔』は、議論劇の体裁を取りながらも、各人物の描写が、要となる言葉の選択や言葉遣いにまで至ってなかった。
『想いはレンズを通って~ハリーと呼ばれたカメラマン~』はドキュメントドラマの体裁をとりながら、一代記から透けて見えてこなくてならない、時代や人間関係の批評性を読み取れなかった。
『こんにちは 赤ちゃん』はミュージカルという体裁をとりながら、歌詞パートがシーンの心情説明に終わっていたため、世界観のクオリティを感じなかった。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

内藤裕敬(南河内万歳一座)
『バベルの塔』は、根気良く書いていらっしゃる。後半は、もう根気だけで書いている。根性がある。しかし、何故、後半を根気と根性で書かねばならなくなったのか? 戯曲賞の審査を題材にした物語だが、その内容が、20代の劇団員が、安居酒屋でボヤいている域を出ていないからだ。どうせなら、もっとメチャメチャな演劇批判に根気と根性を使うべきだ。「言われなくても、わかっている」そう思いながら読んじゃったよ。
『桜の秋』。作者は、何本もの作品を書いているのだろう。モチーフを遊び、広げて楽しむことを知っている。その中で、劇構造を、どう組み立てようか? それも遊んでいる。しかし、それ等が少しずつ甘い。おお! ここから演劇的になるのかな!? と思った所から、テレビドラマ的な、わかりやすさへ逃げてしまっている。ユウレイが便利に使われて、オレオレ詐欺の青年が、実はユウレイの息子だったというのがいらない。息子なのか? 息子かも知れない? 息子だったらどうしよう? その程度で良かったじゃないかなあ。とは言え、私は好きですね。この作風。
『空谷の湧水』はよく書けていると思いました。ちゃんと台詞になっている。戯曲とは、書くことで書かないことを表現しなければならない。書かないことで、より多くを表現できないかにチャレンジせねばならない。この作家は、それを心得ている。しかし、それだけではダメだ。どうも設計図通りに構成されている。壊す作業が無い。飛躍しなればならないことはないが、面白い発展が無ければ、登場人物が粛々とその役割りを記号的に持ち込んで来るだけだ。楽しめないチェーホフみたいになる。そこに自覚的となれば、相当な作品をお書きになるんじゃないのかな。期待しています。
『思いはレンズを通って~ハリーと呼ばれたカメラマン~』は、戦中、戦後を生きた一人のカメラマンの伝記だ。この方は、戯曲にチャレンジして日が浅いのだろうと思いながら読んだ。台詞に面白味と力が無い。個人史をなぞるように物語が進む。ならば、伝記そのものを読んだ方が良い。書く前から、どの言葉にこだわるかを決めてかかっている。どの場面の会話も色が変わらない。あるキャラクターと言葉たちに閉じ込められてしまっている。そうすると、登場人物が生き生きとしてこない。けれど、相当の熱意を持って、この作品に取り組んだことは読みとれた。書き続けて下さい。
『ミュージカル こんにちは赤ちゃん』はおそらく、女と男、仕事と子育て。それが、作者の身近なテーマなのだろう。そこからの出発は大変よろしい。しかし、それを叙事的に展開するのなら、ポイントで叙情が生きて来るだろう。物語が、現実の表層をすべって行く。その分、わかりやすいが奥行きが見えない。会話の後に歌。それも、会話の内面を歌で吐露するくり返しになっている。会話で何をやり、歌で何をやるのか? そこの専門性に欠ける。そこさえ踏み込めば、メリハリのある作品となったろう。可能性のあるテーマと物語だけに、そこが残念ですよ。
今回、最終候補作は5作品。どんなに少なく見積っても、このうち3作品を、私だったら最終候補に残さない。これが残るのであれば、私が下読みした中に最終まで残しても良い作品が何作かあった。確かに力作、野心作が数多く応募される。その中から台詞と会話を生きている何者かが語っているかどうか? 作者の中の困難が、物語をキリリとさせているかどうか? しっかりと選考すべきだと思いました。来年に期待します。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 中屋敷法仁(柿喰う客)
中屋敷法仁(柿喰う客)異なる価値観が混ざり合い、様々な諸問題を抱える現代の「日本」。この複雑な題材に対し、どのような視点をもって描いたか。そして「日本」の観客の前で上演すべき作品なのか。そのふたつに重点をおいて審査を担当した。今回も数多くの未発表戯曲が集まったが、残念ながらどの作品も「最優秀賞」受賞という結論には至らなかった。
『空谷の湧水』は比較的よく書けており、人物描写や物語の展開が巧みであったことは否定しない。しかし果たしてこの戯曲が、劇場という空間で、俳優の身体を使って上演すべきものなのか、という疑問が残った。描かれる内容はオーソドックスなものであり、驚きや面白みに欠けていた。
その点では『桜の秋』は演劇としての企みに満ちており、上演されるのが楽しみになるものだった。ただ、劇中に仕掛けられたトリックやギミックの細かい調整が稚拙で、舞台作品として上演することは難しく感じた。この2作品が特別に「佳作」の受賞となったのは、それでも今後の可能性を感じられたからだ。
『想いはレンズを通って~ハリーと呼ばれたカメラマン~』は、劇世界は丁寧に描いてはいるが、ストーリーの展開、それを支える会話のやりとりがあまりにも単調だった。舞台作品の脚本としての密度が足りなかった。
『ミュージカル こんにちは赤ちゃん』はミュージカルという形式をとる必然性、即ち、なぜこの言葉をメロディに乗せるかが最後までわからなかった。労働、結婚、出産という諸問題も扱い切れていない。
『バベルの塔』はシチュエーションこそ期待させるものだったが、人物にも会話にも全く魅力がない。作家のワンアイディアで終わってしまっていた。最終候補作品は総じて、戯曲としての体裁を整えているだけの印象で、社会や時代を挑発するような野心を感じられなかった。劇場という小さな空間から世界を描き出す、そんな魔力をもった傑作と出会いたかった。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 宮田慶子(青年座)
宮田慶子(青年座)全51作品の中から、最終選考には5作品が残り、結果的には、残念ながら優秀賞の該当作品はなく、「佳作2作品」という結果になった。
題材への執着や切り口の明確さ、人物設定や全体構成やセリフの言葉選びなどの技術面も含め、バランスよく高いレベルに届くのはなかなか困難なことである。
曖昧なシーンの設定が、全体を間の抜けた印象にも、身勝手な表現にも見せたりする。たった一言、たった一つの仕草で、観客の理解をミスリードすることもある。
大胆かつ慎重に、幕開きから終わりまで書き貫く“タフさ”を持って欲しい。
『バベルの塔』は、 “審査”に対する作者の考え方が見えない。審査に当たる「劇作家」たちも、審査会で交わされる言葉も、稚拙すぎて現実味がなく、何を揶揄しようとしているのかわからない。題材に対する劇作家の誠意として、しっかりとした姿勢を持つべきだ。
『想いはレンズを通って〜ハリーと呼ばれたカメラマン〜』は、基本的には“脚色”に当たるだろう。原作に対する敬意は感じられるが、それに添いすぎていて、劇作家としての視点が弱い。客観の役割の新聞記者が単なる「讃美者」になっている点が、ドラマを平板にしている。背後にある激動の時代との重ね合わせが曖昧で、一代記の広がりがない。
『ミュージカル こんにちは 赤ちゃん』は、あえてミュージカルにする意味はあったのだろうか。「仕事と育児の両立」「女性の人生選択」という題材に深く切り込めずに、“出来事”を追うだけの展開になっている。セリフと歌詞内容が重複するので、ドラマが停滞する。もっと飛躍があっても良いのかもしれない。
佳作となった『桜の秋』は、盛りだくさんなモチーフを持ち込んで、青春時代の夢を軸にした二人の女性の人生模様をエンターテイメントに仕立てた。幽霊に法則がなくご都合主義になったり、全てを因果付けしようとする無理がある。幽霊に使命や目的を持たせると、芯ができるかもしれない。
『空谷の湧水』は、台詞に生活の中の言葉としての“癖”があり、独特の空気感を生んではいるが、人物相互の距離感が掴みにくい。精神的に追い込まれた女性、過去を避けて生きる男、福島や処分場など、「疲弊した現代」と「湧水」との関係が明確になりたい。
戯曲は、演劇におけるすべての舞台表現の“土台”だ。
だからこそ、緻密な計算、言葉へのセンス、客観性のある推敲能力と、首尾一貫した作者の思いに支えられた、信頼の拠り所となる戯曲を期待する。
----------------------------------------------------------
文化庁委託事業「平成29年度次代の文化を創造する新進芸術家育成事業」
日本の演劇人を育てるプロジェクト 制作:公益社団法人日本劇団協議会
文化庁委託事業「平成29年度次代の文化を創造する新進芸術家育成事業」
日本の演劇人を育てるプロジェクト 制作:公益社団法人日本劇団協議会