日本劇団協議会は、文部省認可の現代演劇で唯一の社団法人として、 1992年(平成4年)6月30日、新劇団協議会を母体として設立されました。 その後2008年(平成20年)12月の公益法人制度改革関連3法の施行を受け、 2012年(平成24年)3月、内閣総理大臣より公益社団法人の認定を受け、同年4月1日に登記いたしました。 現代演劇の振興に関する事業を行い、演劇創造団体間の交流・連携を図り、 芸術文化の発展向上に寄与することを目的とし活動しております。

人間ひとりひとりはとても弱い生き物です。ライオンやトラやゾウと1対1で対峙したら絶対に勝てないでしょう。その弱い人間が、なぜ地球上で生き物の頂点とも言える位置に立っているのか? それは弱いがゆえに、強いものに立ち向かうために、言葉を発明し、集団で連携して生き延びてきたからです。しかし今、世界は分断と対立が加速し、人と人とのつながりが希薄になってきています。また、日本でも少子高齢化や孤独と孤立が社会の大きな問題となってきています。
そんな状況の中で、演劇は何ができるのだろうか?
日本劇団協議会と加盟する劇団は、現代社会と向き合って、時には観る人の心を癒し、時には勇気づけ、時には新たな視点を与える作品をつくり続けてきました。同時に、さまざまな事業を通して、演劇の普及に努め、演劇に関わる人材の育成を後押しし、多くの社会的課題と向き合ってきました。また、演劇創造環境を少しでも良くするために、文化庁等に提言し、対話の場を持ってきました。
演劇の大きな社会的役割は、「人と人とをつなげる」ことだと私は考えます。
分断と対立、孤独と孤立が拡大しているなか、今こそ演劇が力を発揮する時だと思います。特効薬とはいきませんが、じわじわと効き目が現れる漢方薬として働きたいと思います。日本劇団協議会は公益法人として、多くの演劇人と力を合わせ、今こそ演劇の力で、大きな時代の転換期にある社会に向き合っていきます。
皆さまの、ご理解とご協力を心よりお願い申し上げます。
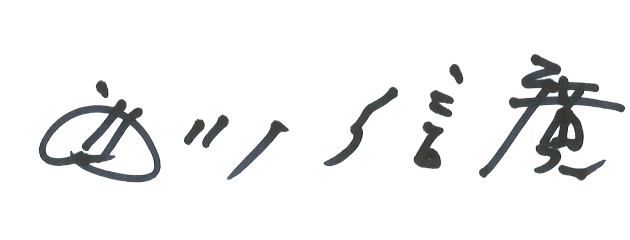

新型コロナ蔓延の影響で世の中は人と人とのつながりが希薄になりました。演劇はそれを少しでも回復する社会的役割を担うことが出来ます。「やってみようプロジェクト」の経験と実績を踏まえて、「劇団間の交流」「劇場との交流」「地域間の交流」「国際交流」など交流をテーマに新たな事業展開の可能性を探ります。

障害がある方の芸術鑑賞をサポートする仕組みの普及に努める「バリアフリー委員会」文化庁「全国キャラバン事業」に対応した具体的立案を行う「キャラバン委員会」、演劇鑑賞会の窓口としての「全国演鑑連劇団会議」を設置し、あらゆる人々が演劇を享受できる社会を目指して活動しています。

次代を担う演劇人を幅広く豊かに育成していくために、どのような人材、どのような事業展開が必要なのか。多彩な職種の人材を念頭に置きながら、主催事業「日本の演劇人を育てるプロジェクト」を中心に、その具体的な方策について検討し、既存事業の見直し、新たな事業化を進めています。

「すべての学校に演劇を!」を合言葉に、主に高校生を対象とした青少年向けの「巡回公演」の実施と、その拡大を図っています。また、学校での「コミュニケーション授業」「ワークショップ」など、教育分野において「演劇に何ができるか」、その可能性を探るとともに、その基盤整備に努めています。

会員団体の「上演記録」をはじめ、現代劇発展のために必要な調査や課題解決の提案などに力を入れています。近年ではコロナ禍での実態調査、ハラスメント防止のための「リスペクト・トレーニング」の導入、劇団概要調査などを実施しています。

演劇界のその時々の話題や時の人、演劇界を取り巻くさまざまな課題などを広く共有できるように、機関誌『join』を年に3~4号、編集発行しています。また、当協議会の活動や情報などを多くの人に知ってもらえるよう、コンテンツの充実を図りながら、公式サイトの更新に日々努めています。
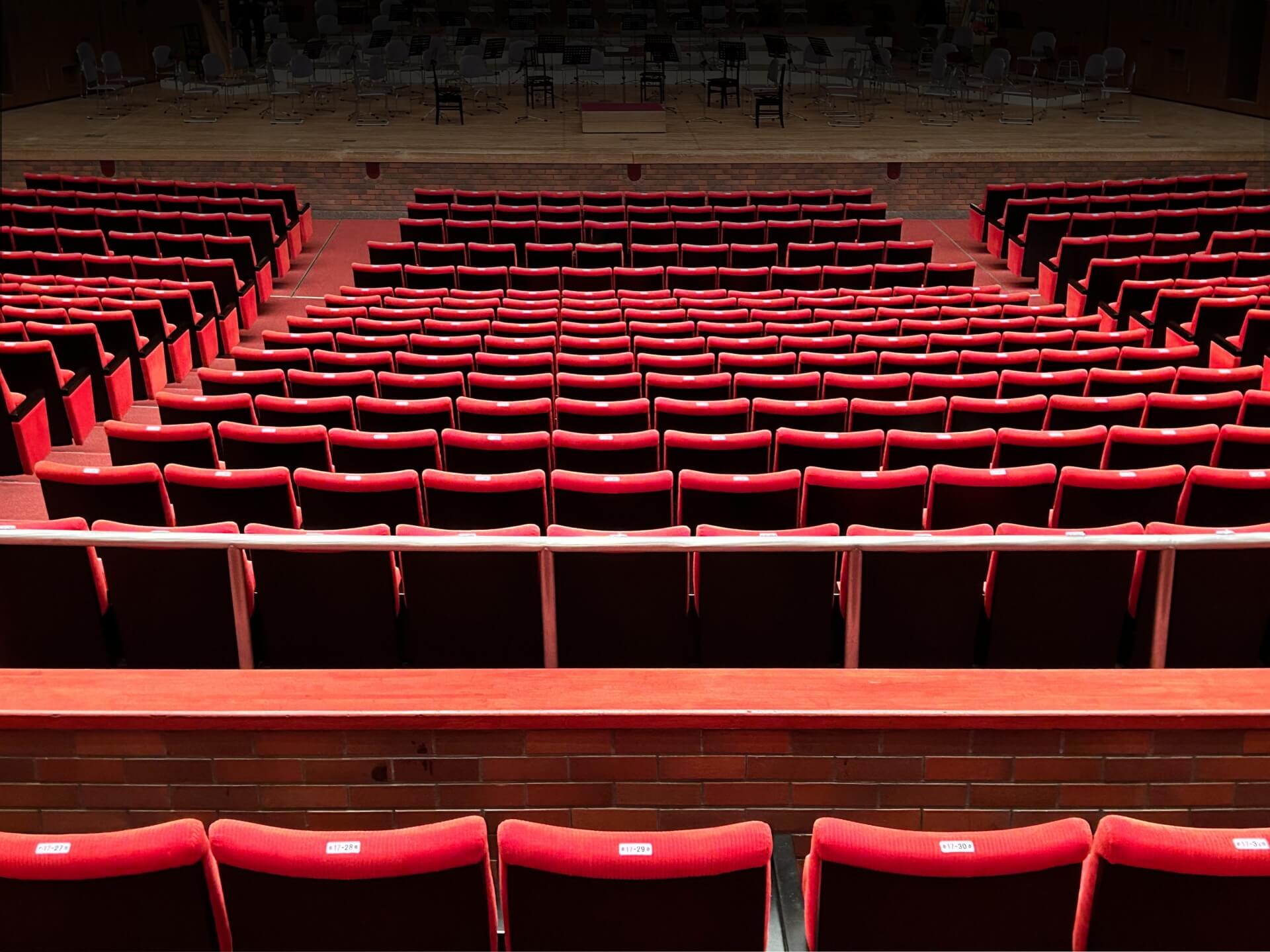
我が国の文化政策の現状を「文化芸術推進基本計画」や「文化審議会」での検討内容に即して学びながら、統括団体としてさまざまな課題解決に向けた具体的提言ができるよう検討を重ねています。特に「演劇の必要性」のエビデンスが求められる中で演劇の魅力をどう打ち出すのかが課題です。

当協議会加盟の各劇団を取り巻く環境が厳しさを増すなかで、新規加盟の呼びかけをどのように進めるのか、また公益社団法人としての組織の在り方などについて、我が国の文化政策を見据えつつ今後の展開を見通しながら「常務理事会」を中心に検討し、改善を図っています。